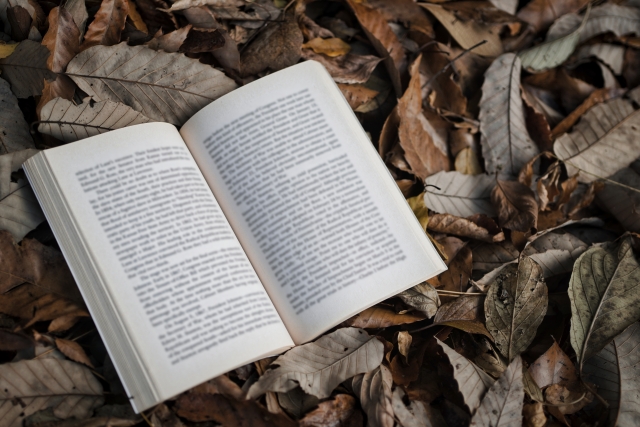Amazonでは社内の方針検討の資料はパワポ禁止でワードの6ページ程度のメモによるとされています。その趣旨は言語できちんと理解して意思決定するというものですが、それを実効あらしめるための方策として、ミーティングの冒頭20~30分出席者全員が6ページメモを黙読するともされています。これにより事前に読むことができなかった参加者も含めて全員が同じ土俵で議論ができるようになります。
興味深いのは一部の省庁で伝統的に行われているミーティングでの行動で同様の趣旨によるものではないかと思われるものがあることです。省庁において通常は方針検討のための資料はやはりワード等の文章によるものですが、これをAmazonのような黙読ではなく、担当者が音読する方式があります。これは強制的に担当者の声は聞こえてくるという意味ではAmazonの黙読よりも徹底しているとも言えます。いずれにしても古今東西で本質的なことは変わらないということではないでしょうか。
ノウハウ
語学の習得における読みの重要性
語学の習得について従来から日本人は読めるが話せないので会話の練習が必要と言われることが多いのですが、結論から述べると読みが足らないから聞くのも書くのも話すのもなかなか上達しないのではないかと思います。
まず会話が成り立つためには相手の発言が聞き取れることが必要ですが、ここで読めるのに聞き取れない場合の多くは読むスピードが聞くスピードに追い付いていないと思われます。聞くスピード以上のスピードで読めるようになって初めて聞き取れるので、対策としては読む練習を沢山するということになります。
次に書くと話すについてもシンプルですが、表現のストックがないとアウトプットはできません。これも対策としては幅広い分野の文章を読むということになると思います。
上記は母国語を考えてみればある意味当然のことで、文部科学省の調査によれば小学校だけでも教科書のページ数は9,000近いとのことで、他にも読んでいるとすれば、外国語を学ぶ際にも少なくとも1,000ページの単位で読む必要があるのではないでしょうか。